
アリスの可変定電圧ミニ・レギュレーター(miniReg)の巻き その3
アリス 「こんにちはー、みみずく先生。」
みみずく 「やあ、アリス。久しぶりだね。」
アリス 「レギュレーターの製作に手間取っちゃいまして。」
みみずく 「成果は出たのかい?」
アリス 「もちろん。じゃーん。観てください♪アリスのminiReg(+)とminiReg(−)です♪」
みみずく 「おぉ、よくできてるねえ。コンパクトにまとまってるじゃないか。」
アリス 「今回は自分で基板を発注してみたから大変でした。
DRCがダメだとか、何度もやり取りがありました。ちょっとへこたれそうでした。」
みみずく 「ははは、私も最初はそうだったよ。けっこうすぐに慣れるもんだから、大丈夫だよ。」
アリス 「配線パターンの見直しとか、小さいのにそれなりに手間がかかりました。
ケミコンボードのときは簡単だったのにー。」
みみずく 「いい経験だったじゃないか。」
アリス 「少しだけ工夫したところがあるんです。」
みみずく 「どんなところだい?」
アリス 「まずNFBモードとnon-NFBモードをジャンパー・ピンで切り替えられるようにしました。
これで実験がしやすくなります。これが回路図です。」
みみずく 「なるほど。」
アリス 「あと、通常のワイヤー配線のためのホールも設けたんですが、それとは別に、
三端子レギュレーターの正電圧用78xxシリーズと負電圧用79xxシリーズのピン配置に準拠した端子ホールも設けました。」
みみずく 「いいアイディアだね。」
アリス 「基板の幅を23mm、高さを39mmに抑えたので、ちょっとしたスペースがあれば三端子レギュレーターと置き換えができます。
もちろん通常基板と同様、ネジでの固定もできます。」
みみずく 「なかなか、実用的にできてると思うよ。」
アリス 「それと、逆電圧から回路を保護するダイオードを付けられるようにしました。」
みみずく 「おぉ、すばらしい。そいつは教えてなかったなぁ。よく気がついたね、アリス。」
アリス 「えへへ…、勉強しましたー♪」
みみずく 「実用上、とても大切なことだ。」
アリス 「と、いうわけで、なんだかんだと、時間がかかってしまいました。」
みみずく 「機能を増やすと、とたんに設計がややこしくなるからなあ。性能が落ちる場合も多いし。私もいつも悩むところだよ。
で、もう試してみたのかい?アリス?」
アリス 「はい!それを話そうと思って♪」
みみずく 「どうだった?」
アリス 「ギター・アンプのキットに使ってみたんですが…。すごーく良くなりました♪
なんか、切れがあるというか、音圧があるというか…。
三端子レギュレーターと比べると、音の味わいがよりわかる気がします。
ちなみに、わたしの場合はnon-NFBモードがあいました。
ちょっとした違いなんだけど、NFBモードよりギターが伸び伸び歌うような気がします。」
みみずく 「良かったじゃないか。」
アリス 「あ、それでね、みみずく先生」
みみずく 「うん?」
アリス 「教えてもらったとおり、トランジスターをいろいろ変えてみると、音がかなり変化しました。
いまのところ、みみずく先生ご推薦の2sc1815と2sc3421の組み合わせがいい感じです。
切れがあって、しかも甘い中域がでます。これ好き。
他にオススメな、よさそうなトランジスターはありませんか?ネット通販でみてても良くわからなくって…。」
みみずく 「うーん、そうだな…。音の良いトランジスターはどんどん製造中止になってるからなぁ…。
小信号用の2sc2240、2sc2362、2sc2458や電力増幅用の2sc4793、2sc5200あたりはまだ手に入るんじゃないかな?
まあ、実際に試してみるまでわからないんだが、メーカーによっても色がある。
トランジスターの製造を中止したメーカーのものでも丁寧に探すと見つかる場合も多い。
ジャンク屋に置いてあるような古いトランジスターも面白い。そんなに高いものじゃないし、いろいろ試してみるのが面白いよ。
ただ、聴いてみてわかると思うけど、2sc1815と2sc3421の組み合わせはレベルが高くって、かなりのゴールデンペアっぷりだ。
これを超えるのはそれなりに大変だとは思うよ。」
アリス 「うむむ、長い道のりになりそうだわ…。」
みみずく 「ははは、いいのを見つけたら教えてあげるよ。」
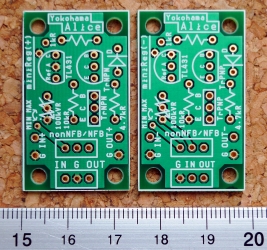
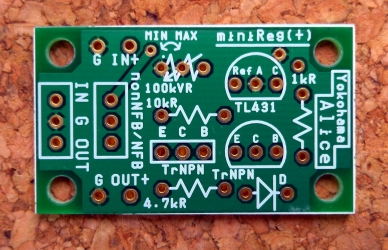
.jpg)
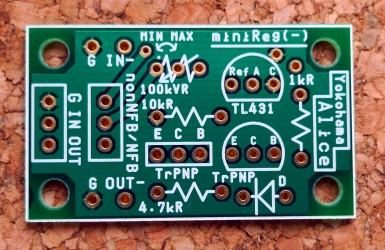
.jpg)